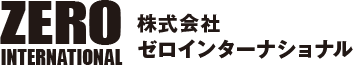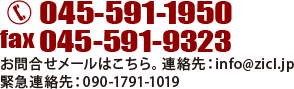Blog
2025年04月15日 [ゴミ屋敷 お役立ち情報]
モノが捨てられない、、、それって病気かもしれません!

突然ですが、以下に当てはまるものはいくつありますか?
①興味のあるモノを次々と買ったり集めたりしてしまう。
②片付けたり整理整頓をするのが苦手で、部屋が常に散らかっている。
③無料でもらえるサンプル品等を、必要でないのにもらってしまう。
④着なくなった服や使わなくなモノを「いつかまた使うかも」と取っておく。
⑤モノをどこに置いたか覚えるのが苦手で、何度も同じモノを買ってきてしまう。
⑥必要なモノと不必要なモノ等、優先順位をつけて判断するのが苦手。
⑦たくさんのモノに囲まれていると安心する、ストックがたくさんないと心配になる.
⑧モノを捨てることに罪悪感を感じる、または手放すのに大きな困難・苦痛を覚える。
⑨溜め込んだモノで部屋が埋め尽くされ、生活するのが困難になっている。
⑩他人に自分のモノを勝手にさわられたり、処分されたりするのは絶対に嫌だ。
②片付けたり整理整頓をするのが苦手で、部屋が常に散らかっている。
③無料でもらえるサンプル品等を、必要でないのにもらってしまう。
④着なくなった服や使わなくなモノを「いつかまた使うかも」と取っておく。
⑤モノをどこに置いたか覚えるのが苦手で、何度も同じモノを買ってきてしまう。
⑥必要なモノと不必要なモノ等、優先順位をつけて判断するのが苦手。
⑦たくさんのモノに囲まれていると安心する、ストックがたくさんないと心配になる.
⑧モノを捨てることに罪悪感を感じる、または手放すのに大きな困難・苦痛を覚える。
⑨溜め込んだモノで部屋が埋め尽くされ、生活するのが困難になっている。
⑩他人に自分のモノを勝手にさわられたり、処分されたりするのは絶対に嫌だ。
いかがでしょうか?3~4個当てはまるという方は少なくないと思います。
特に40~50代以上の方は、多少忘れっぽくなったり、昔の価値観で「もったいない」と思ってしまったりするのは仕方のないことです。
しかし5~7個以上当てはまるという方は、危険信号です。油断すると部屋がゴミ屋敷になってしまう可能性があるので注意が必要です。特に⑦~⑩の項目が当てはまる方は、何らかの疾患・障害があることも考えられます。実際の病名などは医師が診断するものですので、ここでは参考までに、考えられる疾患や障害をまとめてみたいと思います。
「ため込み」に関連すると思われる疾患・障害
発達障害(ADHD/ASD)
注意欠如多動症(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)といった特性が、[ため込み]に影響を与えている場合があります。以下のような場合が該当します。
・モノを整理する、作業の段取りを考えて行うことが苦手
・必要性や価値の優先順位をつけて判断することが苦手
・対人関係が難しく、興味がモノへ向きがち
・興味が限定的で、何かにはまると、それを繰り返したくなる傾向がある
・モノへの執着が強く、壊れたり、実際に使ってはいなくても、手放すことが苦手
強迫症(OCD)
モノを捨てることに強い抵抗・苦痛を感じる場合、強迫症や不安障害の可能性があります。
・ゴミの中に、何か大切なモノが混ざってしまっていたら大変だと思い捨てられない
・生活用品など自分にとって欠かせないモノが、なくなってしまうことを恐れるあまり何個もストックしてしまう
・手放したら後悔するのでは、二度と手に入らないのではという思いが強すぎて、捨てられない
うつ病、双極症障害
いわゆる「そううつ病」の鬱の状態になると、何をするのも億劫で、すぐに疲れてしまい、何もする気にならないためごみなどを溜め込んでしまうことがあります。
・モノに執着はなく、意識的にため込んでいるというよりも、気力がなくて片付けたりごみを出したりすることができず、結果的にため込んでしまう
認知症
高齢者の増加とともに認知症も増え続けており、認知力が低下するにつれて正常な判断や整理整頓などが難しくなる傾向があります。
・買ってきたことを忘れる、モノを置いた場所を忘れる、等の理由で同じモノを何度も買ってきてしまう
・不安な気持ちが強くなり、「何かあった時のために」とものを溜め込んでしまう
そのほかの疾患
身体の病気、ケガ、障害等によって、身体の自由がきかなくなり、片付けたり重いものを運んだりするのが難しくなる場合もあります。また、統合失調症などの精神疾患によっても、正常な判断が難しくなることがあり、幻覚や思い込みでモノが捨てられなくなってしまうことも考えられます。

以上のどれにも当てはまらない場合、「ため込み症」かもしれません
ため込み症(ホーディング障害)とは、不必要なモノを過剰に蓄積し、捨てることが困難な精神障害の一種です。上記など他の精神疾患や障害ではうまく説明できないのに、精神的な要因によってモノをため込んでしまい、生活に支障をきたしている状態です。上記のような疾患と併発し、より困難な状態に陥っている場合もあります。
2013年公開の「米国精神医学会」の診断基準で明確に定義された疾患で、主な診断基準としては以下のようなものがあります。
①モノの価値とは関係なく、モノを捨てることが極端に困難である
②モノを捨てることにより生じる不安や苦痛、ストレスが極めて高い
③蓄積されたモノにより生活スペースが侵害され、本人や家族の生活に支障が出ている
症状には個人差があり、ため込むモノも、新聞、雑誌、書類、チラシ、レジ袋、包装紙、空き箱、衣類、靴、レシート、文房具などさまざまです。単なる「収集癖」、または「片付けられない人」と思われてしまうことが多く、本人やその家族、そして時に医療者も「ため込み症]という精神疾患を認識していない場合が多いのが現状です。
「ため込み症」の治療

この疾患の治療については、まだ標準化されたものはないようですが、主に薬物療法と認知行動療法が重要な役割を果たすと言われています。ただ、多くの患者が「自分が病気だとは思っていない」または「他者とのコミュニケーションが苦手」という傾向があり、診療を受けることも拒むケースが多いようです。
この場合、他者が一時的に部屋を片付けてもまた同じ状態に戻ってしまうことが多く、片付けることよりも患者の心理的な問題を取り除くための治療が必要です。そのためには精神科医のほか、家族や心理師、ソーシャルワーカーのような相談員など、支援してくれる人がいると望ましいです。
まずは地域の精神保健福祉センターやカウンセリングセンター等に相談し、適切な介入を行ってもらうことが治療の第一歩ではないかと思います。
参考:
OCDサポート「3-7.ためこみ、ゴミ屋敷と精神疾患」
MSDマニュアル家庭版「ためこみ症」